
地上デジタル奮闘記 その2
2009/05/05 ←その1 その3→ ホームページへ戻る
地デジ生活が始まってはや1年がたちます。その間ハイビジョンレコーダもグレードアップしました。 W録となりハードディスクも800GBになりました。
[2台目ハイビジョンDVDレコーダ SHARP AQUOS DV-ACW38 (2007年3月23日購入)]

地デジ環境としては、アンテナレベルは決して高くはなく、時折ブロックノイズが発生することはありますが、頻度はそれ程高くはなく、概ね満足のいくものでした。しかし前ページでも少々言及していますが、地上アナログの画質がかなり落ちました。恐らくUHFとの混合により干渉を受けているものと思われます。混合をしていない時はきれいに映っていたからです。もっともUHFとVHFの混合自体は極めて普通のことであり、それ自体問題がある訳ではないので、うちの特殊な環境が影響しているものと思われます。
しかしアナログは殆ど見てないので、それ程気にしていなかったのですが、今年の4月より両親との同居が本格化しました。両親部屋のテレビは依然アナログテレビです。年寄りなので画質にこだわりがないようで、別に何も言ってないのですが、改善してあげたいという気持ちがありました。が、やはり何も言われないと行動に移せないですね。
ところがどうしてもアナログ画質を改善しないといけない事態が発生しました。私も含め家族が テレビ出演することになったのです。家内が小遣い稼ぎにある民放の視聴者参加番組に応募して当選したのですが、所謂ドッキリカメラのようなものでした。私がだまされて、家に隠しカメラがしかけられていて、まんまとはめられたのですが、放映される内容はちゃんと完成したものを見せてもらって同意の上、放映されるます。単なる多数で出演するものと違い、しっかり私の家族が中心(それこそ私は主役のようなもの)に描かれていて見ごたえのあるものでした。これは是非ともしっかり放映を録画したいと思った訳です。ハイビジョン放送なので、基本的には地デジで録画するのですが、コピープロテクトのないアナログでも録画しておけば人にも配布しやすいと思ったのですが、どうせ録画するなら高画質で残したいのが人情です。
そんな訳で急遽地上アナログ画質の改善に取り掛かった訳です。放映は2007年11月19日(月)です。UHFと混合させなければいいのは分かっているので、この放映を録画することだけに注力するなら、一時的に配線を変えることでも対応できますが、前述のように両親のためもあり、恒常的な環境としたいと考えました。両親はNHK BSも非常に気に入っているということなので、その要望にも答える必要があります。その結果以下のような配線になりました。
[配線図⑦ VHFとUHFを混合しない配線]
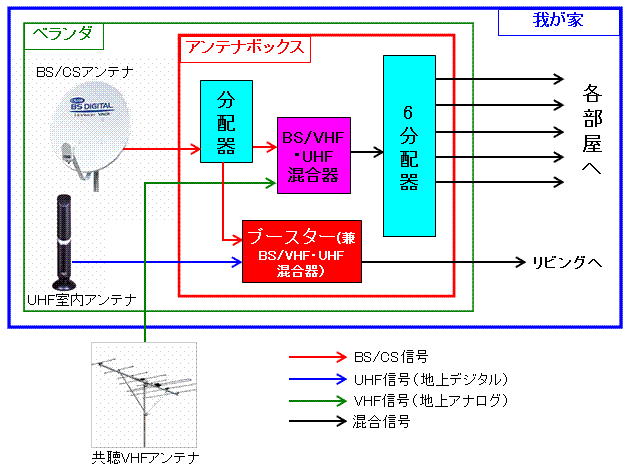
これで両親部屋のアナログテレビで、高画質な地上アナログとBSアナログが見られることとなりました。勿論最大の目的であった家族出演放映も無事きれいな画質でビデオにも録画することができました。(当然ハイビジョンでも録画し、来るべきBru-rayレコーダ導入時に Bru-rayに残す準備もしました)
着々とハイビジョン環境を整備してきましたが、依然ディスプレイはハイビジョン対応とは言え、32型ブラウン管のままでした。フルハイビジョンには程遠い水平解像度800本程度です。まあブラウン管ならではのプラズマや液晶にはない良さもあるのですが、解像度の低さは如何ともしがたいところです。もうかれこれ2年以上大画面薄型テレビを物色し続けていましたが、ついに購入を決意しました。最後までプラズマと液晶で悩みました。それぞれ一長一短でしたが、やはり消費電力が決め手となり、液晶を選択しました。液晶とするなら 東芝のREGZAと決めていました。画質もさることながら、USBハードディスクに録画できる、DLNAクライアント機能があるなど、機能面でも最新の技術を惜しみなく投入していることが主な理由です。
[フルハイビジョン液晶テレビ
東芝REGZA 52Z3500(2007年12月15日配送)]

サイズは50インチ以上と決めていました。やはり画質は最高ですね。すぐにはUSBハードディスクは導入しませんでしたが、ネットワーク接続はいろいろと試してみました。Web閲覧などもできますが、これははっきり言って使い物になりません。遅すぎです。まあ高機能は追々使っていこうと思います。
さてREGZA導入により、今まで使っていたブラウン管ハイビジョンテレビは 両親部屋(和室)へお下がりすることにしました。その結果地デジを見る部屋がひとつ増えることになったので、配線も変更する必要が出てきました。既述のように我が家のブースターは出力が2つあるので、それ程面倒な変更をすることなく、2部屋地デジ対応にすることができました。配線は以下のようになります。
[配線図⑧ REGZA購入後]
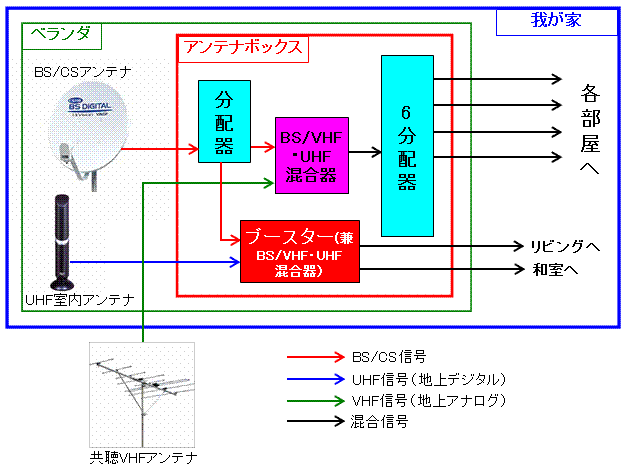
アンテナボックスの状況も以下のようになりました。
[REGZA購入後のアンテナボックス]

正直かなりごちゃごちゃですが、これは前述の地上アナログ画質改善対応によるところが大きいです。
大画面フルハイビジョン薄型テレビが導入されれば、もう残るはこれしかありません。ハイビジョンレコーダはずっとSHARP製を使ってきたので所謂愛着のようなものがありました。しかしSHARP製ハイビジョンレコーダは市場での評判がそこぶる悪いです。評判はパナソニックやソニーが圧倒的に高い状況でした。それでもハイビジョンレコーダは極めて多機能なので、メーカーを変えると思わぬところでデグレードを起こします。あるメーカーでは当たり前の機能で廉価版にも搭載されているようなものが、他のメーカーではフラッグシップ機にもないという例は枚挙に暇がありません。
それでもリサーチを十分に実施した結果、やはりメーカーを変えることにしました。評判が非常に高い パナソニック製です。今回私が譲れない機能として、 iLinkで他のレコーダから TSムーブする機能があります。前述のテレビ出演番組をDVDレコーダーに録画してあるので、それを移してBru-rayに焼きたかったからです。その結果ソニーは全く選択肢に入りませんでした。ソニーはどうしてこの機能付けないのでしょうね。最近のソニーは首をかしげる製品が多いです。
[初のBru-rayレコーダ パナソニック
DIGA DMR-BW830(2008年12月21日購入)]

ただハーディスク容量は以前のものより落ちてしまいました。1TB機ははっきり言って高過ぎです。現在のHDDベアドライブ市場の500GBハードディスクと1TBハードディスクの価格差(約3000円)を考えるとレコーダが7,8万円高いのはどうしても納得できません。結局1TB機(フラッグシップ機)はあきらめ、500GBの中堅機にしました。
とにかく多機能なのに驚きです。懸念していたSHARP機からのデグレードは殆ど気になるものはありませんでした。全く無かった訳ではありませんが、殆ど別の機能で代替可能であり、何よりそんなものを補って余りある、驚きの高機能です。特にネットワーク機能の高さは驚愕しました。ただ反応の遅さはネットでも大変不評でしたが、これは確かに少々閉口しますが、まあ我慢できる範囲です。
早速テレビ出演録画番組のSHARPのDVDレコーダからムーブして、Bru-rayに焼きました。それ以外にもBru-rayレコーダ購入を見越して、1年近く前から重要な番組は消さずに、またDVDに焼かずに残しておいたので、それらをせっせとムーブしました。
大画面フルバイビジョン薄型テレビがあり、Bru-rayレコーダも持った今、基本的に完全無欠のハイビジョン環境と言いたいところですが、実はそうではありません。逆にここまで機器が揃うと、やはり改めて不完全なアンテナ環境の問題がクローズアップしてきてしまいます。
レベルが基準値ぎりぎりか下の局もあるため、稀ですがブロックノイズが発生します。大切な録画にブロックノイズがあったら台無しなので、ブルーレイに残す番組は全編をしっかり見ないと安心できません。特に我が家は上空を羽田から離陸したジェット機が飛ぶ時があります。騒音は全く気にならないのですが、その際にブロックノイズが発生する頻度が高まります。
2005年に初めて地デジチューナ搭載のハイビジョンレコーダを購入してから4年、室内アンテナで何とか地デジが見られる環境を構築してからも2年半以上の月日が経ちました。その間ひたすら例の共聴アンテナ(某上場企業の社員寮設置)が地デジ対応してくれるのを心待ちにしていた訳ですが、まさに地上アナログ停波が2年近くに迫った今日でも未対応のままとは当初は全く想定してませんでした。あの会社は上場企業のくせに全く新技術に疎い三流企業なんだとあきらめる他ない日々でした。
この間私は本サイトでもご紹介しているように涙ぐましい努力をしてきた訳ですが、それ以外にもいろいろやってきました。ひとつは NHKに相談したのです。昨年(2008年)の夏のことです。電波障害地域なので、共聴アンテナを利用しているため自身ではどうにもならず困っている旨話しました。NHKの言うには地デジはアナログよりも電波障害に強いので、今まで共聴アンテナを利用していた人もぞくぞく独自にアンテナを立てているというのです。特におたくは室内アンテナでもそれなりに受信できているのだから、屋根にアンテナを立ててより安定した受信できるようになる可能性は高いということで、一度アンテナ診断を受けるよう勧められました。
早速Webで無料アンテナ診断を頼んだのです。しかし結果は NGでした。やはり厳しいということでしたが、この診断には疑問が無かった訳ではありません。そもそも家の周辺をうろうろして測定器で測っていたのですが、素人目にももっと高い位置で測定しないと意味がないのではと思っていました。特に電波障害を起こしている某上場企業の社員寮は5階建ての建物なので、それ程べらぼうに高い訳ではありません。うちの屋根から4,5メートルのポールを立てると何とか超えることができる程度です。高くアンテナを立てれば何とかなるように思えてならなかったのですが、一応向こうもプロなので、プロが診断した結果ならそういうことなんだろうと諦めた訳です。
ところがところがです。今年(2009年)の3月、ふと向かいの○山さん宅を見ると屋根の上に地デジのアンテナが立っているではないですか。このお向かいさんも我々と同様に某社員寮による電波障害を受けていました。我々と違って当該社員寮が建つ前から居たので、元々共聴アンテナからケーブルが引かれていましたが、当然地デジに関しては我が家と同じ問題を抱えていた訳です。位置的にも我が家と条件は殆ど同じです。
[地図2]
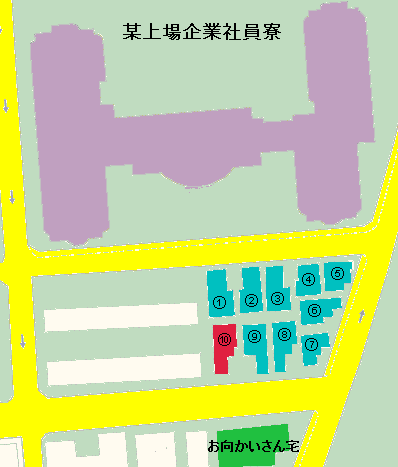
我が家(赤の⑩の家)の向かい側(南側)の家(緑色)がお向かいの○山さん宅です。丁度真北方向(地図では真上)にある東京タワーからの電波に対する障害条件はほぼ同じであることが推測されます。
この家は年寄り夫婦二人暮らしで、母が挨拶を交わす程度で全くと言っていい程付き合いはありません。老夫婦のみなので、恐らく息子さんか誰かが立ててくれたんだろうと思います。従って詳細(どういう経緯で立てることになったか、実際受信状況はどうなのか)を聞くことはできないと思って、何も聞きませんでした。一応母に、きれいに見られているかだけはちょっと尋ねてもらったところ、きれいに見られてるとのことでした。
あのアンテナ診断は何だったのか。まあ費用を取られた訳ではないので抗議できる筋合いではないですが、プロなど信用できない。いやプロなんていないのだと思い知りました。
これでうちでもアンテナ立てれば見られると確信し、もはや診断なしで立ててもらうことにしました。勿論先の診断をしてくれた業者とは別の業者を頼みました。一応見積もりには来てもらいました。特に屋根に上るのに特別難しいといった事情もないので、工事は基本料金(アンテナ代、屋根馬、ポール、設置費込み)の19,800円で実施してくるとのこと。ただブースター(25,000円)が見積もりに入っていました。先のアンテナ診断のこともあったので、プロの意見でも鵜呑みにしないと決めていたため、これは独断で断りました。今ある室内用のブースターで十分。もしかしたらこれもいらないかもしれないし、そもそも利得を高めるために屋外アンテナ立てるのに現在以上の能力のブースターが必要になるのは本末転倒と考えたからです。また見積もりのブースターはUHFだけでなく、VHFもBSもブーストするタイプでした。これには不誠実さを感じました。見積もり時にBSはブーストなしで使っているのを見ておきながら、高いBS対応のブースターを見積もりに入れるなど、この業者も決して信用はできない。万が一ブースターのグレードアップが必要な場合でも自分で調査して最適なものをネットで格安で買おうと思い、とにかく設置だけしてくれればいいということで工事をお願いしました。
4月26日(日)、昨日の大雨とはうって変わって快晴ですが、風が非常に強く工事可能か心配しましたが、問題なかったようで、14時40分到着するとすぐに始めてくれました。2名で見えました。
[アンテナ工事の様子]

アンテナボックスの配線まで含めて1時間強で終了です。アンテナボックスと配線は以下です。
[地デジアンテナ設置後のアンテナボックス]

[配線図⑨ 地デジアンテナ設置後の配線]
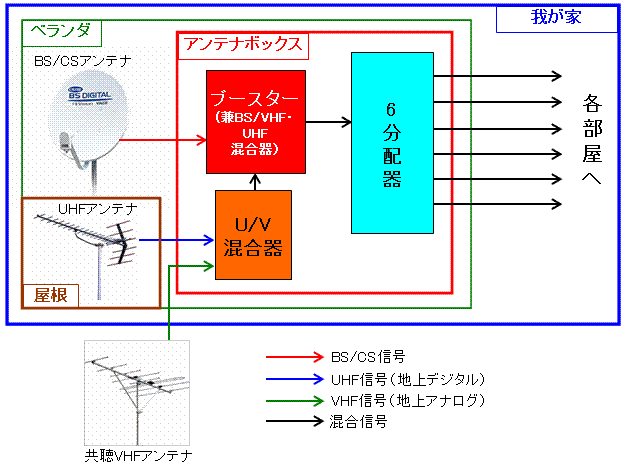
配線も大分すっきりしました。設置後は地デジのアンテナレベルは劇的に改善しました。DIGA、REGZA、AQUOSのいずれも視聴基準値を10~30以上超えています。出力の高い広域局よりも、出力が低く今まで難があった地方局の改善が著しいです。今まで全く見られなかったTOKYO MXが基準値差10以上で綺麗に見られるようにもなりましたし、チバテレビも基準値以下ですが映ります(まあチバテレビはどうでもいいですが)。ただしTVKだけは広域局以上に改善度が低いです。共聴アンテナにおいてVHFアンテナと一緒に立っているUHFアンテナとの関連もあると思われますが、元々限界値に近かったのかもしれません。
以下に各機器でのアンテナレベル改善状況を表に纏めました。因みに屋外アンテナ1がブースターをつけていない状態で、屋外アンテナ2がつけたものです。アンテナレベルの値は各社で異なっているので、絶対値よりは改善度、及び基準値との差を見てください。ただ基準値の置き方も各社明確ではありません。しかし超えていれば絶対いいという訳でもないようです。やはり安定させるには基準値を 10以上超えている方が好ましいようです。ただ逆に基準値超え10以上であれば十分で、表の20以上という項目は「超安定」と書いてはいますが、あくまで改善度を分かりやすくするための参考値です。またアンテナレベルは同じ機器、同じ局でも日、時間によって結構変動します。一応以下はできるだけ平均を採取したものです。尚、アンテナレベルとは信号の強さではなく、S/N比を表現するのが普通です。
[アンテナレベルの改善状況]
機器名 |
基準値 |
NHK総合 |
NHK教育 | TVK | 日本テレビ | テレビ朝日 | TBS | テレビ東京 | フジテレビ | TOKYO MX | チバテレビ | 放送大学 | |
| DIGA DMR-BW830 | 44 | 室内アンテナ | 49 | 49 | 42 | 44 | 48 | 43 | 49 | 43 | 18 | - | 50 |
| 屋外アンテナ1 | 63 | 64 | 45 | 57 | 59 | 60 | 63 | 59 | 38 | 12 | 66 | ||
| 屋外アンテナ2 | 77 | 76 | 49 | 68 | 74 | 72 | 75 | 72 | 56 | 35 | 80 | ||
| REGZA 52Z3500 | 43 | 室内アンテナ | 49 | 49 | 38 | 42 | 50 | 40 | 48 | 49 | 21 | - | 46 |
| 屋外アンテナ1 | 56 | 58 | 47 | 59 | 54 | 51 | 59 | 55 | 38 | 14 | 54 | ||
| 屋外アンテナ2 | 63 | 64 | 54 | 58 | 58 | 58 | 63 | 63 | 56 | 38 | 57 | ||
| AQUOS DV-ACW38 | 60 | 室内アンテナ | 60 | 53 | 56 | 60 | 62 | 57 | 58 | 56 | 18 | 6 | 57 |
| 屋外アンテナ1 | 78 | 77 | 56 | 72 | 75 | 77 | 76 | 78 | 47 | 12 | 79 | ||
| 屋外アンテナ2 | 83 | 79 | 64 | 75 | 79 | 80 | 79 | 80 | 75 | 35 | 81 |
|
視聴不能 |
基準値以下(ノイズ発生頻度高) | 基準値~10未満(ノイズ発生の可能性あり) |
| 基準値10~20未満(安定) | 基準値20以上(超安定) |
大きく改善されているのがよく分かると思います。ただ広域局でも局によって結構ばらつきがありますね。またリビング内でのアンテナ接続順序は、DIGA→AQUOS →REGZAの順、つまりレコーダ優先で接続しています。このことがアンテナレベルの絶対値や改善度に影響があるのかと思ったのですが、一応REGZAを先頭に接続して測定してみたところ、上記と変わりなかったので室内での分配損失の影響は殆どないようです。
表でも分かる通り、ブースター設置の効果は依然あったので付けました。TOKYO MXなどはブースターがないと基準値以下になってしまいます。決して十分なレベルという訳ではないのでしょう。しかしこれ以上の能力をもったブースターにする必要は全くありませんでした。やっぱり見積もり信用できないよね。
また今回の屋外アンテナ設置にあたって、今まで電波障害となっていた建物との位置関係が分かる写真を撮ってみました。
[屋外アンテナと障害建物との位置関係]

左側の今設置中のアンテナが我が家のアンテナで、向こうに見える建物が某上場企業の社員寮である電波障害の元になっている建物(5階建て)です。この建物の遥か先に東京タワーがある訳です。アンテナの高さは建物の高さを超えてはいないのが分かると思います。これくらいにできれば今回のようなアンテナレベルは確保できるということですね。この建物が7階以上あったら、こうはいかなかったかもしれませんし、10階以上ならほぼ絶望的でしょう。
因みに右に見えるアンテナ(BSアンテナも付いているやつ)が、今回屋外アンテナ設置のきっかけになったお向かいの○山さん宅のアンテナです。高さもほぼ同じです。
たった2万円でブロックノイズとはおさらば、安定受信が可能となりました。やっと、やっと、やっと正真正銘の完全無欠のハイビジョン環境が完成しました。長かったなぁ、グスン!
因みに設置したアンテナは、DXアンテナ USA-25Dです。20素子の中堅製品ですね。ステンレス製でないのがちょっと気になりますが。まあいつかもっと良いのに(高利得&ステンレス製など)に変えてもいいですね。
[地上デジタル対応UHFアンテナ DXアンテナ USA-25D]

さて完全無欠のハイビジョン環境にはなったのですが、実はやはりUHFと混合するとVHF、つまり地上アナログの画質は悪くなってしまう現象は起こりました。室内アンテナで無理矢理受信していたことが影響していると考えていたので、今回の屋外アンテナ設置で改善すると目論んでいたのですが、依然混合すると写りが悪くなります。
まだ我が家もアナログテレビは残っています。今は両親部屋もハイビジョン環境なので、子供部屋のテレビがそうです。一応25インチのブラウン管なので、画質の良し悪しは分かりますし、結構この部屋で過ごすことも多いので画質は良い方がいいです。一応予定ではここ1年以内にアナログ環境は殆ど無くしてしまおうと思っていますが、ここへきて逆にアナログ環境が恋しいという不思議が現象が起きています。(まあデジタル環境が整備できた余裕の表れかもしれませんが)
そんな訳で前回地上アナログ画質を改善した時と同様に配線の見直しをしました。
[配線図⑩ 地上アナログ画質改善後の配線]
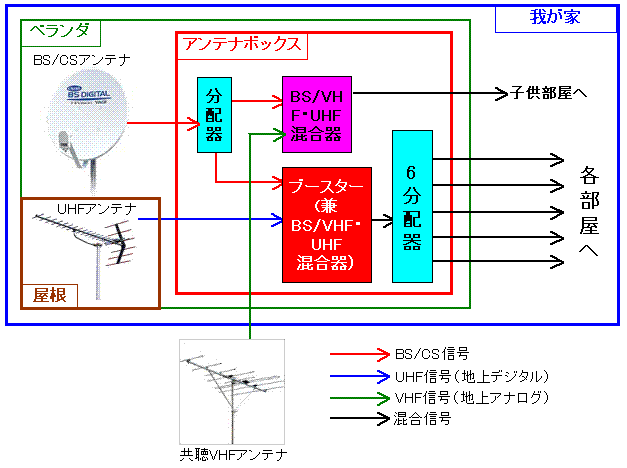
[地上アナログ画質改善後ののアンテナボックス]

機器数としては、UV混合器がなくなって、分配器とBS/UV混合器が増えたのでひとつ多いのですが、UV混合器が非常に大きかったので、返ってすっきりした感じです。
しかし更に翌日VHFを分配してデジタル環境の部屋へも地上アナログの信号を送信するように変更しました。すべての機器で地上アナログも受信できるようにしたのです。もちろんデジタル環境はUHFとの混合になるので、画質は悪いですが受信は可能です。これまでの配線は殆どがデジタル環境の部屋にはアナログ信号を一切送っていませんでしたが、今後は地上アナログ信号もいくことになりました。まあそれで何がうれしいかというとあまり無いのですが、たとえばデジタル環境部屋にもVHSビデオデッキなど地上アナログにしか対応していない機器があり、これらの時刻合わせは地上アナログ放送から実施しているので、この時刻合わせができるようになったことくらいでしょうか。まあ自己満足といったところです。
[配線図⑪
UHF屋外アンテナ設置後の最終形配線]
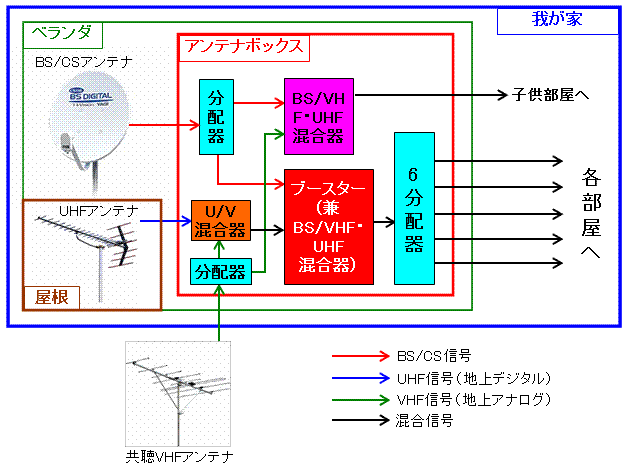
[UHF屋外アンテナ設置後の最終形のアンテナボックス]

かなりごちゃごちゃになりました。まあ地上アナログ停波までは、しかたないですね。
いずれにしても劇的に改善したテレビ視聴環境、うれしくて笑いが止まらないです。。。
今度は逆に共聴アンテナがまだまだ地デジに対応「しない」ことを願うようになりました。え?だってやったことが無駄になちゃうんで。。まあどうでもいいけど。。